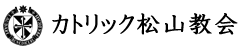それも12月25日を過ぎると、いつの間にか人々の関心からクリスマスが薄れ、にわかキリスト教国もやがては暮も押し詰まった年の瀬に、人々は雑踏に身をまかせて「大みそか」の除夜の鐘まで正月の準備にいそしみ、仏教国・神道国に衣替えするのです。
ところで、教会はこの時期を待降節から降誕節として、神が人類に示された偉大な業を思い起こし、感謝と記念を表わす季節としています。
そして、降誕祭後の最初の主日、つまり今年は12月30日を「聖家族の主日」と定めて、キリスト者の生活が各々の健全な家庭生活によって育まれていくことを確認し、お互いに存在の大切さを見直して反省し合うことを勧めているのです。
教会の玄関や聖堂の「馬小屋の聖家族像」に象徴される聖家族のイメージは、私たちに愛らしいクリスマスロマンを伝えてくれますが、A・B・C各年の聖書日課が示すこの日の福音の箇所は、必ずしもそれほど甘い話ではなく、むしろ聖家族が出くわした、しかもヨセフ、マリア夫婦にとっては親として苦い思い出となった出来事を伝えています。
彼らの生活を支えていたのは、すべてを受け入れて神の計画に従う絶大な信頼と信仰でした。聖家族のシンボルは、互いの人格を尊重し労苦を共にする夫婦であり、信頼の絆で結ばれている親子、兄弟、姉妹が肩を寄せ合うすべての家族を、神が豊に祝福して下さっていることを表しています。
ところが、近年の経済優先の考え方から、物の豊かさを求めてきた私たちの生活は、いつの間にか純粋に日本的な年末・年始の風情を味わうゆとりさえ失いかけるほど、精神面での生活が貧しくなり、さらに情報の氾濫で、なにが真実か分からなくなるほどの流動的な世相や、家庭の中にあっても不信に悩むようなことが多くなってきました。
お互いに信頼で結ばれた潤いある生活を望むならば、ありのままの自分に返ることができる家庭にあって互いの人格を尊重し合うことであり、それは神の言葉に素直に耳を傾けて、その息吹を感じて生活すること。
つまりキリストの呼吸を知り、そのリズムとテンポを家庭生活に築くことから始まるのです。
新しい年を迎えての初めての火曜日。みなさんはどんな思いを抱いてミサに与り、どんな祈りをなさるでしょうか。
もちろん、それらの思いや祈りはさまざまであり、人と同じほどの数があるというのは言うまでもないでしょう。
しかしどれほどの数があろうとも、また人によって如何様に異なっていようとも、ともかく、私たちの旅は新しくまた始まったのです。
聖書が告げる信仰者とは、なによりもまず、「旅人」なのです。
旅というものが、現在の私たちになじみ深いなんとかツアーと呼ばれる観光旅行とはおよそかけ離れたものだということは、改めて言うまでもないでしょう。
旅は人にその使命をかけることをも要求してきます。その意味で、旅とはまさに冒険でした。
「信仰者とは旅人である」とはどれほどでしょうか。もし、天国旅行会社発行の安全保障つき切符を手に入れたような気分になっているとするなら、それこそ大変なことです。
ヘロデ王をはじめエルサレムの人々はみんな、不安になったとういう福音が朗読されますが、この不安は何だったのでしょうか。
自分の今の生活が変えられてしまうことへの不安、言い換えれば、生活の隅々に至るすべてを自分の手の中に持っていたいということからくる不安だったのではないでしょうか。だから、彼らは決して旅立とうなどとは思いません。彼らは今の生活を変えたくないのです。
しかし、よく考えてみると、旅立つことから信仰は始まるのではないでしょうか。たった一つの星を頼りに旅立った3人の博士たち。彼らの旅の途中にどれほどの不安と危険が伴ったのだろうと思い至ったとき、美しい話だなどと、のん気に構えてはいられなくなりました。
新しい年を迎えて、私たちは何を頼りに、どんな旅をしようとしているのでしょうか。
典礼は、私たちみんな "共同体"の祈りです。第二バチカン公会議以後、典礼は変わりました。公会議前の典礼は生き生きとした人々の参加よりも、美しく荘厳な儀式であることが重視され、儀式についての大変細かい規則がたくさんつくられました。
しかし、公会議は、典礼が本来、司祭と信徒を含めた共同体全体がキリストと共に捧げる礼拝であることを強調します。
典礼は聖職者の独壇場でもなければ、個人的な祈りの場でもありません。それはいろいろな機関がそれぞれの役割を分担しながらひとつに結ばれている(キリストの)体全体の公的(公の)な礼拝行為なのです。
それゆえ、公会議は典礼における信徒(信者)の共同的、積極的参加を重視します。
また、規則づくめで儀式化してしまった典礼が、共同体の生き生きとした自発的な賛美の場になるように、多様性と自由な適用の可能性を広げました。
典礼の中心は常にキリストです。そこで、マリアや聖人の祝日から意味のあまり明確でないものが典礼暦から削除されたり、ある地方では聖堂内に数多く飾られていた聖人像が一部取り除かれたりしたところもありますが、それは "マリア信心"や "聖人崇敬"の価値を低く見ているわけではありません。
しかし、すべての中心がキリストであることを、いくら強調しても強調し過ぎることはないと思います。
キリスト中心ということ、それと同時に憲章が強調するのは、「御ことばです」。「典礼行事のなかで聖書は最も重要なものである」と述べているように信仰の糧であり、泉である聖書は秘蹟や典礼の意味を明らかにし、信じる私たちの答えを呼びかけます。典礼になくてはならないものです。
公会議以前にはミサの中心はどちらかと言えば聖変化だけにあって、あとは付け足しのように考えられていたところもありました。
「ミサに遅れて来ても、説教が終わるまでに入れば主日の務めは果たされた」などとも言われていました。
憲章は「聖書が教会で読まれるときキリスト自身が語るものである」と述べていますが、ミサの中で私たちは聖書と聖体の両方でキリストに接し、キリストに養われるのです。
典礼について二言
憲章は聖書朗読を聖体の食卓になぞらえて、「神のことばの食卓」と呼んでいます。
教会の宣教や司牧の活動も全て典礼と深く結びついていると思います。だからこそ、典礼が本当に生き生きとした信仰の表現であり、日常生活に豊かな力を与える恵みの場となるようにしなければなりません。
例えば聖書朗読が本当に深く心に沁みこむように読まれるのと、何を読んでいるのか意味もつかみにくいほど下手にされるのとでは大きな違いが出来てきます。
「ローマ・ミサ典礼書の総則」(INSTITUTIO GENERALIS MISSALISROMANI)の第3章の「特別な奉仕職」の中の99番には「朗読奉仕者は、福音を除き、聖書を朗読するために選任される」とあり、そのことに関連して次のように述べられています。
101「選任された朗読奉仕者が不在の場合、聖書の朗読を行うために他の信徒が任命される。この者は、この役割を果たすのに真にふさわしい者で、十分に準備されなければならない。こうして、信者は神のことばの朗読を聞いて、聖書の快い生き生きとした感銘を心に受けることができる」
102「……その務めを正しく果たすために、詩編唱者は詩編朗唱の技術と正しく発音して唱える能力を備えていなければならない」
107「典礼における役割は司祭や助祭に固有のものではなく、……主任司祭や教会主管者司祭によって選ばれたふさわしい信徒にも、典礼で行われる祝福あるいは一時的な任命によってゆだねることができる……」
138「使徒信条を唱え終わると、司祭は席で立ち、手を合わせ、短い勧めのことばによって信者を共同祈願に招く。続いて、先唱者か朗読者か他の者が、朗読台もしくは他のふさわしい場所から会衆に向かって意向を述べる……」
以上のことでも分かるように重要なのは聖書朗読者で、神のことばを人々の心の糧となるように分かりやすく、意味深く朗読するために十分練習する必要があると思います。
アナウンサーや俳優になる人は、こうした練習を何年もする訳ですが、教会で神のことばの朗読は少し簡単に扱われ過ぎているのではないでしょうか。
朗読者も、オルガニストなどと同じように典礼の奉仕者としてある程度の資質と技術が必要ですし、訓練、練習も必要なのです。ただ一生懸命に読めばよいというものではありません。
典礼は教会の要ですから、よい典礼はよい教会を育てることになるでしょう。その意味でも神に奉仕するため、自由な気持ちで朗読奉仕者が増えてくるように__。松山教会は、そういう教会であるように努めたいものです。
クリスマスには一般の人も大勢来ますが、イースターは、どちらかと言うと久し振りの信者の人たちが多いのではないでしょうか。
久し振りに教会に来る人たちにとって、教会は「敷居が高い」とよく言われます。みんなばらばらで共同体なんてものじゃない、と思っている "毎週組"でも "久し振り組"から見れば、なんとなくみんな模範生に見えるそうです。
毎週組の中には、たいした理由もなく、さぼったり、遅刻したり、いつも後ろに陣取って終わるとそそくさと出て行く人がいます。
一方、毎週組をうらやましく思い、「敷居が高く」なった教会にやって来られた久し振り組が、今日もいらっしゃるでしょう。さらには、ご復活ぐらいごミサにあずかりたいと願いながら、病気で、家庭の事情で、それが出来なかった欠席組も少なくないでしょう。
考えてみれば、主の復活の記念である日曜日のミサが、ただ、あずからねばならないものから、あずかれて幸せと思うものにならなければ、どの組の人も、ミサにあずかっても、主の復活にはあずかっていないのかもしれません。
反対に、もしその実感があれば、ミサの時間に台所に立たねばならなくても、ベッドから出られなくても、主の復活にあずかる信者なのだと思います。
「主の死を思い、復活をたたえよう、主が来られるまで」という歌声が、音として天井に響くだけなのか。こころの底からわき上がる喜びの叫びにしたいものです。
イエスさまが『命のパン』と言われる、そのご聖体の意味が、私たちに分かっているでしょうか。分からないまま、ただ惰性で聖体拝領をしてはいないでしょうか。
ご聖体をいただくことの意味をかみしめて拝領しているか、「聖体拝領」に、どのような意識と信仰をもっているか、もう一度自分に問いかけられる「チャンス」を与えられているようです。
現実のパンは、食べるとお腹がいっぱいになるから、力になっていることが分かります。でもご聖体をいただいても、何も感じないので、ご聖体で満たされるとはどういうことか、ぼんやりとしてはっきり分かりません。
それは私たちがご聖体の力を体験してないからです。ご聖体は本当に「命のパン」なのでしょうか? ご聖体には本当に力があるのでしょうか? ご聖体は何ですか。
聖変化のときに、司祭がパンを高く上げて「みんな、これを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される、わたしの体(からだ)である」という言葉を唱えるとき、そのパンはご聖体に聖変化します。
その瞬間に神の力によって、実際にその変化が起こるという神秘を私たちは理解し、信じているのでしょうか? ミサを捧げている司祭はどうでしょうか? あなたたちばかりでなく、司祭にもその神秘が本当には分かっていないのかも知れません。
しかし、例えミサを捧げている司祭が聖変化の神秘を分かっていなくても、ミサの中で、その司祭の手と祈りを通して、その瞬間に聖霊が働き、聖変化は確実に起こるのです。
これこそ、叙階の秘蹟の力……叙階された司祭だけに神が与えられた力です。司祭は、叙階の秘蹟の力によって、パンひと切れの中にイエスを現存させ、イエスご自身がご聖体となって私たちの体の中に入ってくださり、ご自分の命を私たちに与えてくださるのです。
「キリストの体」という言葉をもってご聖体を渡されたとき、受ける私たち(みんな)が「キリストの命」をいただく……と思って拝領すると、それは変わってきます。
「体」と言われると、どうしても物質的な体と受け取ってしまう人が多いようですが、そうではなく「命をいただく」という自覚をもってご聖体を拝領するとき、受ける人の意識が「主の命」を渡されているのに、使う言葉が「体」なので、器としての体の「イメージ」を持ってしまい、それでご聖体がピンとこないのかも知れません。
パンが生きる糧だった昔の人は、ご聖体をもっと分かっていたのですが、現代の私たちは物質文明に浸っている中で、分からなくなってしまっています。
私たちが「命のパン」を食べるとき、イエスさまご自身を私たちの内にお迎えするのです。
命そのものであられるイエスさまは、私たちの一つひとつの細胞に命を与え、体のすみずみまで生かしてくださるのです。
私たちの傷める細胞も、器官も、心も、精神も、あの素晴らしいイエスさまの命に満たされて生き返るのです。
一粒の薬でも体を癒やすのです。イエスさまの命には、それよりずっとずっと力があるのではありませんか。
全能の神、生ける神、イエスさまご自身が私たちの体の中にはいって来てくださる!。こんなに素晴らしいことが現実なのです!。
私たちの中で、ご聖体の力、キリストの命が働くときには当然、私たちに変化が起こります。
キリストの命を自分の体の中にお迎えし、その力が働きだすのですから、当然、癒しは起こります。
大きな癒しや奇跡も期待できるのです。地上におられたときのイエスさまが何をなさったか、思い起こしてみましょう。
私たちの内に現存される、その同じイエスさまが、私たちの苦しみを黙って見ていることなどなさるでしょうか。
「何をしてほしいか」と聞いてくださるのではないでしょうか。イエスさまに叫んだら、きっとあの力を働かせてくださるでしょう。キリストが私たちに期待される信仰を、はっきりと表わしていかなければなりません。
体が癒やされるだけではありません。私たちはキリストの命で満たされるのですから、こころも精神もキリストの命で癒やされるのはもちろんのことです。
心の重荷はイエスさまが引き取ってくださいます。いろいろなことに縛られている私たちを解放してくださるのです。
イエスさまが、私たちの悩みや問題を解決してくださいます。苦しみを喜びに変え、主の平安を与えてくださいます。
キリストの命は、私たちから輝きだし、その喜びが生き生きと表れます。私たちの生活は変化します。
私たちは毎日キリストの似姿へと変えられていくのです。私たちは神の力を受け、神の道具として神のために働かないではいられなくなります。 (以上)
このみことばは、キリストが私たちに与えられた『掟』です。優しさの中に、ピリッと引き締るような語感が漂ってきます。『友のために自分の命を捨てる』という、大きな愛についても教えられています。今号は、その「愛し合う」ことの前に立ちはだかる、私たちのことについて考えてみましょう。
喜び勇んで洗礼を受けた人が、間もなく元気をなくして、教会に来なくなってしまうことがあります。このような方があなたの周りにいらっしゃいませんか?
「なぜなんだろう」…それが司祭の悩みの種なのですが、その原因の一つは、新しい信者が信仰の先輩である信者たちにつまずいてしまう、ということがあるのです。
教会とは、美しく見えて、きれいな社会であると思っていた人が、いざ中に入って共に歩んでみると、とんでもありません。中傷、悪口、かげぐちが多いのにすっかり驚いてしまいます。派閥があって互いにいがみ合っている、という話も聞こえてきます。
パウロによれば、初代教会にも分裂があって、人々は互いに争い合っていたと伝えられています。ましてや複雑な現代社会の中で、教会にそれがあっても不思議ではないでしょうが、そのようなことが多くの人々のこころを傷つけていることは確かなようです。
互いに非難し合い、攻撃し合うならば、その連鎖反応はなかなか止むことはないでしょう。キリストは『裁いてはいけない』と言われていますが、教会ではその裁きが目立ち過ぎます。自分のことは棚に上げて、つい、人のあら探し(悪いところをあげつらうこと)をしている、ということはないでしょうか。
ミサのたび毎に「兄弟に向かって罪をおかしました」と告白し、また「主の平和」と互いにあいさつをしているのに、その舌の根も乾かないうちに、兄弟姉妹を責めたり、いじめたり、陥れたりしているのです。
私たち人間の罪の根というものは、なんと深くはびこっているものなのでしょうか。なにかの折に人を裁き、人を罪に定めるという人間の醜さが表に出てくることは、とても悲しいことです。
群集心理とは恐ろしいものです。一人では出来ないことも、五人、六人が集まると意外に残酷なことをしてしまうのが人間です。
社会では、多くの人から袋叩きのような目に合い、どうしても人に対して、信頼や期待を持てなくなってしまった、という人の話も聞かされます。それがこじれて、ときには復讐心や憎しみを抱いてしまうのも無理からぬことです。
裁くこころ…石を投げるこころこそ、キリストが最も嫌われ、戒められた〝醜いこころ〟です。愛は一方的ではないのです。例え自分で善いことをしていると思っても、それが一方的な行為であれば、石を投げるという結果を招いてしまうのです。
キリストの『愛』とは、どれだけ自分を相手の立場におくことができるか、という問題なのです。人の苦しみ、痛みを理解し、共感し合うという態度なくして、どうしてキリストの道を歩むことができるでしょうか。
病気で苦しんでいた多くの人々は、イエスに触れようとして彼の傍に押し寄せました。キリストが指し出された、その優しい『愛の手』を思い起こしてみましょう。
いま、未信者の人が教会に多く訪れるのは、結婚式、葬式、クリスマスのときくらいでしょうか。日曜日には意外と見かけません。しかしそれは、悩み苦しんでいる人が少ないからでしょうか。それとも、癒してくださるキリストの愛を、私たちが周りの人々に十分伝えていないからでしょうか。
日々二ュース聞いていて、さまざまなことで悩み苦しんでいる人々が大勢いることは間違いありません。愛されていること、認められていること、自分自身の価値、安心感、必要とされていることなどを自覚できずにいる人々が多いのです。
こころの深いところで孤独感を抱き、生きる喜び、人の命を支える喜びなどを実感していない人々も多いようです。
その人々に私たちが伝えようとしているのは、倫理的な教義や堅くるしい教会の決まりごとなどではありません。
今一度、福音書に『生きた姿』として表わされている『…互いに愛し合いなさい』というイエスのみことばを深く味わい、周りの人々に対する態度をきちんと見直していきましょう。回心のために照らされる光と勇気を祈り求めます。
もともと「アーメン」は、ヘブライ語で「まことに、真実に」という意味の言葉です。昔から、祈りの結びとして「そうです。その通りです」という意味で、先唱者が唱える祈りについて、会衆がその祈りの内容に賛同していることを表わすための言葉として、会衆一同が「アーメン」と唱和しました。また「そのようになりますように」という願望の意味でもあります。
旧約聖書には「真実、忠実」という意味から、私たちを救ってくださる神は、決して約束をたがえられないお方だという意味で「神はアーメン」とか「アーメンである神」という言い方がしばしば用いられています。
それと同じ意味の使い方として黙示録には、私たちを救ってくださる神を讃える言葉として「アーメン」と賛美しています(5・14、7・12、19・4、22・20)。
新約聖書には、イエスが大事なことを話す前に、これから話すことが重要で、間違いのないことだということを表わす意味で、語り出しの言葉に「アーメン…!」とおっしゃっています(マタイ8・11,10・5など)。口語訳では「あなた方に、よく言っておく」と訳されています。
ミサの中では「入祭のあいさつ」に始まって「派遣の祝福」に至るまで、10数回の「アーメン」が唱えられます。これは司祭が、その都度唱える祈りに、集まった
会衆一同が賛同して、同じ心で祈っていることを表すために、「アーメン」と唱えるのです。
ローマミサ典礼書の総則には「会衆は、嘆願に心を合わせ『アーメン』と答えることによって、この祈願を自分のものとする」とか、感謝の祈り(結びの栄唱?神の栄光への讃美が表されるところ)では「会衆が『アーメン』と答えることによって、これを確認して結ぶ」などと説明しています。
ですからこの「アーメン」は、会衆一同の積極的な参加のしるしとして、大きな声で、しかも力強い「アーメン」であってほしいものです。
古い記録によると、その昔、ローマの教会のミサで「アーメン」の声が雷のように轟いたと、聖ヒェロニモが書いています。
また聖体拝領のとき司祭は、ご聖体を一人ひとりに示しながら「キリストのからだ」と言います。これに対して拝領者は「アーメン」と答え、命(いのち)のパンをいただきます。これは「聖体がキリストの御からだであることを信じます」、「この拝領によって私がキリストのからだ(神秘体)とされることを信じます」と言う信仰告白なのです。
「アーメン」は短い、簡単な言葉です。しかしそこには、とても深い意味と力強い信仰告白が秘められています。
心を込めて、力強く「アーメン」を唱えましょう。
第二バチカン公会議以後、最も目に見えて変わった点は典礼でした。その意味で最初に私たちが公会議の新鮮な息吹を身近に感じたのが、この典礼憲章でした。
それから40何年か経って振り返ってみると、確かに典礼は驚くほど刷新され、新しい典礼がすっかり定着したようです。
あれほど新鮮な感動と同時に、さまざまな論議や時には抵抗を呼んだ日本語の典礼にも慣れて自然になり、かつてラテン語が用いられたことさえ忘れるほどです。
そしてラテン語時代の典礼をほとんど知らない新しい典礼の中で育った信者たちの数も多くなり、新しい典礼はもう〝新しい〟とは言い切れない時代になりつつあるようです。
しかし、他方では典礼刷新の意味について十分な説明や教育が伴わず、表面的な形式の変化だけになって、刷新の意味や意図が良く理解されないまま来てしまったことも否めません。
例えば、以前は祭壇が壁に向き、司祭も信徒も壁の方に向かってミサを捧げていたものが、祭壇が信者の方を向き,司祭と信徒が対面してミサを捧げるようになりましたが、それが歴史的な典礼の研究をもとにして、「主キリストを中心に食卓を囲む共同体」という最初の教会の伝統を土台にした刷新です。
しかしこのことが十分に理解されず、せっかくの対面式も形式も変化に終わってしまっていることが少なくない、と思うのです。
この憲章は公会議の最初に、98パーセントの司教の賛成によって決議されたものですが、それはヨーロッパで百年以上も前から盛んであった典礼研究と典礼運動を背景にしたものだったからです
しかし、そのような背景を持たない日本では、十分な土台なしに、いわば唐突に「上からの刷新」と言う形に流れていったところがあるようです。
その意味で、典礼憲章の精神による刷新は、日本でようやく第一段階の「形の刷新」を終えたところで、これからさらに「内容の刷新」を進めていかなければならないでしょう。
この次では典礼憲章の精神を考えながら、これからの課題についても触れてみたいと思います。
典礼憲章とは……
第二バチカン公会議(1962~1965)で定められた「典礼刷新と促進」に関する諸原則の実践規準。同公会議公文書全集の筆頭に掲げられ、4憲章の一つ。序文に続く内容は次の通り。
第1章 典礼刷新と促進のための一般原則
第2章 聖体の聖なる秘義
第3章 その他の秘跡、及び準秘跡
第4章 聖務日課
第5章 典礼暦年
第6章 典礼音楽
第7章 教会芸術と教会用具。
このように典礼に関するすべてが網羅され、諸原則と諸規準の記述は130項目に及んでいます。
この中の第1章の42項(小教区の典礼生活)では、次のように記述されています。
「司教の代理を務める司牧者のもとに、地域的に設置された小教区は、最もすぐれたものである。それは、いわば全世界に設立された見える教会を表現するからである(中文略)。
小教区の共同体意識が盛んになるよう、特に主日のミサの共同体祭儀において努力しなければならない」。
この典礼憲章は1963年12月4日、パウルス(パウロ)6世教皇の名のもとに諸教父が署名して発布。条例実施に関する指針を定めて翌年2月の四旬節第1主日から効力を発し、45年を経て現在に至っています。
『ミサ典礼の総則』に従い適正に
高松教区の方針に沿って私たちの教会でも発足した宣教司牧評議会は,典礼憲章など教令や指針をベースにした「ローマ・ミサ典礼書の総則」に従って、主日のミサをより適正な方向へ進めるよう努めることになりました。
その一つが、通常の主日のミサの〝司会〟です。当教会ではいつの間にか〝司会〟という名称が定着していたようですが,同総則の中にその名称は見当たりません。典礼において果たす務めの中の「解説者」と混同していたのではないか、と思われます。
「解説者」について、同総則(105番b項)は次のように説明しています。
「解説者は、信者を祭儀に導き、よりよく理解させるために、信者に適宜、簡潔な指示(・・)や説明(・・)を与える。解説者の注意(・・)は正確(・・)で、簡潔明瞭でなければならない(後文略)」。
さらに聖書朗読の緒言(57)でも「解説者の説明(・・)や注意(・・)は、通常書き物にして司式司祭の事前の承認を得なければならない」とあります。また、この緒言に基づく資料では次のように述べています。
「もちろん、すべての典礼にこの解説者が必要である、というわけではない。通常の主日のミサのように会衆一同が典礼の流れや動作にある程度慣れていれば、指示や注意はおのずと減っていく。一方、復活祭やクリスマスのように、普段より多くの信者(未信者)が集まる場合、また未信者が多い葬儀や結婚式などには必要、ということになる」。
以上のように同総則が示す「解説者」の役割や諸説明などを考慮するとき①解説者には正確な指示、説明、注意が伴う②司式司祭の動作や言葉の意味が十分理解されていること―などが求められ、従来のように信徒の誰にでも任命するには難しい面がある、との判断に立ちました。
そこで協力宣教司牧司祭団の同意のもと、去る9月から通常の主日のミサにおいては、担当司祭が必要と認める場合を除いて、解説者(従来の司会者)は置かないこととしました。
感謝の祈り(奉献文)の聖別の少し前、続いてパンとカリスが掲示される時に小鐘を鳴らすことと合わせて2カ月が経過し、皆さんすっかり慣れてきた感じです。「落ちついた気持ちでミサに与(あずか)れます」との声が聞かれますが、いかがでしょうか。
質 問 箱
信徒の方から質問が寄せられましたので、聖人伝なども参考にしてお答えします。
初金曜日のミサ」
「イエスのみ心」が保護者の松山教会は、イエスのみ心の信心と、毎月第1金曜日の信心を合わせ捧げているミサを〝初金ミサ〟と呼んでいます。
これはキリストが十字架の犠牲となられたのが4月の初金曜日だったので、毎月の初金曜日にミサ聖祭に与り、犠牲を捧げるということ。それとキリストが、聖女マルガリタ・マリア・アラコック(1647~90)にお命じになり、お約束されたことに由来するものです。
カトリック聖人伝によると、1673年12月27日のこと。マルガリタがご聖体の前で祈っていると、突然、キリストが現れ「一つは、み心の祝日をもうけること。二つめは毎月の第1金曜日に聖体拝領して祈ること。三つめは信者の家庭でみ心を捧げること」で感謝と贖罪の務めを果たすよう、お命じになりました。それによって天国の幸せに導かれるなど特別の恵みが与えられるであろう、とお約束になりました。
マルガリタは、この信心の普及の務めを果たすために、自分のすべてを捧げました。43歳で天に召された後、「み心」と「〝初金〟」の信心は公認されて全世界に広がり、教会によって奨励されることとなりました。
ピオ9世教皇が1856年、ご聖体の大祝日の次の金曜日を「み心の祝日」と定めたことで、マルガリタの使命はついに完成。こうして1920年、人々の敬愛が深まったマルガリタはベネデクト15世によって、めでたく聖者の列に加えられました。
街に流れるジングルベル、ツリーに色とりどりに光るイルミネーション、教会の中と外に飾り付ける馬小屋、クリスマスケーキを囲む家庭、プレゼントを届けてくれる〝サンタクロース〟の物語…。それらはどれも人間の善意と信頼、喜びと平和の絆を感じさせてくれます。
キリストの誕生を告げ知らせるルカ福音書も『地には平和、御心に適う人(ひと)にあれ』(2・14)と、平和と喜びのメッセージを伝えています。まさにクリスマスのメッセージの中心は「平和」にあると言ってもよいでしょう。
しかし、クリスマスの伝える平和のまことの意味を理解するには、もう一つの降誕物語を思い出してみる必要があるようです。
キリストの誕生を物語るマタイ福音書は、苦悩や疑い、欲望や流血という、人間のどろどろとした世界のただ中に生まれてくるキリストを描いています。
婚約者マリアの懐妊を知ったヨセフの苦悩、権力と支配への欲望に凝り固まったヘロデ王。そのヘロデの悪意から脱出するために夜逃げをする一家。キリストの身代わりに虐殺されるベツレヘムの子供たち(マタイ1・18、2・18)。
決して幸せな誕生とは言えず、むしろ悲劇の物語のようです。それが、あの平和のメッセージと、どう結びつくのでしょうか。
『わたしは、平和をあなたがたに残し、わたしの平和を与える。(ただし)わたしはこれを、世が与えるように与えるのではない。』(ヨハネ14・27)と、ご自身が語っているように、平和を実現するキリストのやり方は全く独特です。
まことの平和は、決して簡単に、安易に手に入るものではなく、苦しみを乗り越え、他者のために犠牲を払う心から生まれてきます。
キリストは、このことを誕生から十字架に至る苦難の生涯をかけて語っているのではないでしょうか。
クリスマスの平和ムードの楽しさを味わうのも決して悪いことではありませんが、合わせて自分の大切な「何か」を他人のために喜んで捧げることが出来るなら、平和のメッセージはより深く、私たちの心を満たし、そこから周りに広がっていくことでしょう。